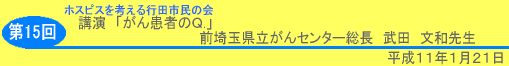私は熊谷生れ。子供の頃から自転車で行田には遊びにきていた。私の二代前は行田生れである。 私は去年の10月11月にカンボジアに行く予定であった。諸般の事情により2月7日に出発。そこでの仕事の元になるお話をしたいと思う。
1950年代にはQOL(クオリティー・オブ・ライフ)といっても判る人はいなかった。QOLとはなにか。がんにならなくてもQOLはある。1950年代には英語にもQOLの定義はなかった。
QOL:一人一人違う→オーダーメイドの医療。恋人や配偶者と同じ(人が何といおうと幸せと思う事が大事)。医療自身が邪魔をしない配慮が肝心。
がんはもともと無症状の病気。がんに冒される事により痛みが出てくる。社会的制約も出現。霊的な痛み・苦しみというものもあるが日本では誤訳されてきた。これは、人生にとって大きな出来事・アクシデントがおきた場合、自分の人生を振り返り解決されない問題に対して心の奥底で痛みを感じ苦しくなる事。
末期ケア→緩和ケア:末期がんでは一つ一つのがんによって数多くの部所から症状が発生。以前はがんを治す事に主眼をおいた治療により数々の痛みに対する治療が見過ごされがちであった。この現実に対してシシリーソンダース女史(イギリス)が疼痛緩和ケアの医療を実現。当時は末期の人が対象であったので末期ケアといわれていたが、現在はその技術を導入することによりがん医療全てのがんの患者さんに通じる医療として緩和ケアと命名された。現在はがん患者だけでなくAIDS、慢性関節リウマチ等にも流用。末期ケアは緩和ケアの一部という認識である。
緩和ケア:治癒を目的とした治療に反応しなくなった患者に対して行うQOLを考慮した全体的な緩和ケア。痛みのコントロール・痛み以外のコントロール・心理社会面からのケア・スピリチュアルな面のケア・家族及び遺族の苦難への対処の支援。
WHOがん疼痛救済プログラム:世界中のがん患者の痛みを開放
目標:現存医療機関網を通して今世紀中に全てのがん患者を痛みから開放する事。
| 1986年から公式に各国政府にガイドラインを提示。 | |
| 第一目標 | 痛みに妨げられない夜の良眠 |
| 第二目標 | 安静時の痛みの消失 |
| 第三目標 | 体動時の痛みの消失 |
| 第四目標 | 痛みの消失が維持され、平常の生活に近づく事 |
| 注意 | 現場で、痛みに対しては正直に訴える事(医療者側に誤解を生む)。 |
痛みがある場合:まず痛み止め。3つの種類・段階に分けた痛み止め治療。作用の強さによって3段階に分かれる。一つ目は非オピオイド二つ目は弱オピオイド、三つ目は強オピオイドで非オピオイドを1とすると弱オピオイドは10というくらい強い。強い痛みに対しては麻薬が適応。医師がそれぞれの痛みに対応したいたみ止めを選択。強オピオイドはモルヒネで、麻薬。普通人の場合とそれを必要とする病人の体の中では同じ麻薬でも全く作用が違う。それを必要としている人(病人)は、体がモルヒネ様物質を生産。しかし、痛みをとるのに十分ではない状態であるところにモルヒネを外から投与することになるので中毒にはならない。
世界にはモルヒネを使えない国がある。ベトナムにも行ってきたが、モルヒネ使用までに8年かかった。日本でも、以前は使い難い状況にあった。1980年代終わりから日本政府は改善されてきている。
がん患者におけるモルヒネの適応:痛み・咳・呼吸困難・下痢
健常者のモルヒネ乱用はお酒でいうと一気のみ。医師の管理下では小さなお猪口でちびちび飲む感じ。
モルヒネ投与:鎮痛有効域では最初の作用は吐き気と便秘。制吐剤、下剤を併用する必要がある。次の毒性発現域の段階で眠気→呼吸抑制となる。末期の薬という認識・習慣性の危惧等の誤解を解く必要がある。しかし、一人一人モルヒネの効力及びその投与量には個人差がある。
モルヒネ投与初期:経口モルヒネ30〜60mg/日→30〜50%増減量してゆく。1〜2%の例では1000mg/日以上となる。
基本原則を守ったモルヒネ長期反復投与:精神依存皆無、身体的依存は漸減法でOK、耐性の発生は緩徐。
がん疼痛治療の倫理:患者には痛みの治療を求める権利がある。→日本のモルヒネ消費量は増大。世界ではアメリカ・スカンジナビア・オセアニアで最も多くモルヒネを消費。日本は発展途上国。モルヒネ先進国でもがんの痛みがまだ存在することも事実。一般国民向けに厚生省と共に「がんの痛みが消えるとき」を出版。
がんが心に与える影響:落ち込み→立ち直りの繰り返し。インフォームドコンセントと緩和ケアが重要。
がん患者による診断名の認知率の推移:1997年98%ががん告知(がんセンター)。反対するのはむしろ御家族。
インフォームドコンセント:医療担当者、とくに医師による説明を受け、患者が自発的な選択、同意あるいは拒否すること。
患者自身にがんを告げない理由:かわいそう、文化信念信仰宗教死生感の違い、告げかたが判らない、心のケアの仕方がわからない。
患者が正しい情報を必要としている理由:半信半疑から脱却したいから。自分の将来計画の為。未解決な心の問題を解決したい。心を開いたコミュニケーションをしたい。死の準備をしたい。
チェック:告げないでおいて大丈夫か?告げられないために本人が誤った自己決定をしてしまうのが気の毒ではないか?だましおおせると考えるのは医療者のおごり。嘘に費やすエネルギーを患者のケアに費やすべき。だれもが心の衝撃から立ち直る力をもっている。
がん告知の実際:1早いうち(なるべく早いときから)、2原則として主治医が、3患者本人に(患者側の同席者は患者が選ぶべき)、4プライバシーの守れる静かな場所で、5礼儀作法に則り悪い知らせのあることを匂わせ、相手の目をみて話す範囲をきめる。
がん患者の治療は根治治療と緩和ケアを共存させる治療。
緩和ケア:入院ケア、在宅ケア、デイケア、コンサルテーションサービス、死別にあたってのケア
「百歳を超えるまで元気に生きて「がん」で死のう!」