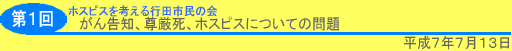院長の挨拶 病院で患者をお世話するということは、単に病気を治すというだけでない。 患者さんは精神的にも弱っているし、家族も突然の大事の出来で、パニック に陥っている。特に、当院のように消化器外科であれば癌が多い。今でも常に 50人からの癌の患者さんの世話をしている。この患者さんたちには告知して いない患者さんもいる。告知の問題は難しい。1人1人の事情、状況に応じて 慎重に決めている。 何よりも患者さん本意に対処している。
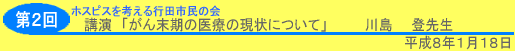 ホスピスの歴史についてから始まり、癌告知の難しさ家族との関係、患者本人の 自覚(80%くらいの人は自分が癌と知っているようだ)そしてこれからは癌末期も
在宅医療が中心になるだろう。 「質疑応答および話し合い」 患者の家族より:病院では先生が忙しく、ゆっくりお話ができない。今日のような 時間をつくって頂けると何でもお聞きすることができて、ありがたい。というような
話しがあった また、薬局経営者より医薬分業は癌末期の在宅医療について有用かと いう質問にたして、院長より医薬分業は医療界の遂勢であり、当院も考えている。勿
論、在宅医療の現場でも有用であると答えた。
ホスピスの歴史についてから始まり、癌告知の難しさ家族との関係、患者本人の 自覚(80%くらいの人は自分が癌と知っているようだ)そしてこれからは癌末期も
在宅医療が中心になるだろう。 「質疑応答および話し合い」 患者の家族より:病院では先生が忙しく、ゆっくりお話ができない。今日のような 時間をつくって頂けると何でもお聞きすることができて、ありがたい。というような
話しがあった また、薬局経営者より医薬分業は癌末期の在宅医療について有用かと いう質問にたして、院長より医薬分業は医療界の遂勢であり、当院も考えている。勿
論、在宅医療の現場でも有用であると答えた。
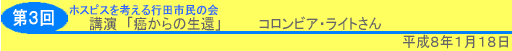 2日前にタイミング良く、読売新聞にライトさんの写真入りで案内広告が載ったので外部より問い合わせも多く天候その他の障害もなく120人収容の会場に130人が押し掛け、超満員となったが関係者も多かったのでビックリした。
市長もこの問題について、生老病死から説きおこして味のある挨拶をされた。 ライトさんの講演はさすがで癌の体験が主体だったが、食堂発生の苦心談など来客者を感激された。
2日前にタイミング良く、読売新聞にライトさんの写真入りで案内広告が載ったので外部より問い合わせも多く天候その他の障害もなく120人収容の会場に130人が押し掛け、超満員となったが関係者も多かったのでビックリした。
市長もこの問題について、生老病死から説きおこして味のある挨拶をされた。 ライトさんの講演はさすがで癌の体験が主体だったが、食堂発生の苦心談など来客者を感激された。
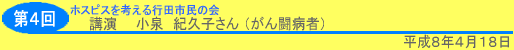 川島院長はこの会の生い立ちと、目指すところ癌末期のケアの難しさホスピスの現状などをはなされた。 講演者の小泉さんは現在66歳、今までは36年間、小学校の教師として結婚する間もない忙しい人生を過ごしてきた。そして9年前突然、悪性リンパ腫にかかり胃を全的。その後は抗癌剤で治療、入院は3回に及んだ。
小泉さんの話しはたんたんと分かり易く静かに自分の9年間に渡る闘病生活を語った。悪性リンパ腫には抗癌剤が効くと言われているが小泉さんのように肝臓に移転したり大動脈に移転に転移したのが消えるのは珍しい例だろう。今でも3日に1回は病院通いだそうである。
事前にPRについては毎日新聞、朝日新聞、行田市広報が案内を出してくれて問い合わせも多く浦和、深谷、熊谷、吹上からも参加者があった。
朝日新聞の4月19日の朝刊に記事として記載された。
川島院長はこの会の生い立ちと、目指すところ癌末期のケアの難しさホスピスの現状などをはなされた。 講演者の小泉さんは現在66歳、今までは36年間、小学校の教師として結婚する間もない忙しい人生を過ごしてきた。そして9年前突然、悪性リンパ腫にかかり胃を全的。その後は抗癌剤で治療、入院は3回に及んだ。
小泉さんの話しはたんたんと分かり易く静かに自分の9年間に渡る闘病生活を語った。悪性リンパ腫には抗癌剤が効くと言われているが小泉さんのように肝臓に移転したり大動脈に移転に転移したのが消えるのは珍しい例だろう。今でも3日に1回は病院通いだそうである。
事前にPRについては毎日新聞、朝日新聞、行田市広報が案内を出してくれて問い合わせも多く浦和、深谷、熊谷、吹上からも参加者があった。
朝日新聞の4月19日の朝刊に記事として記載された。
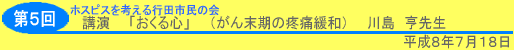 副院長が「おくる心」と題して講演。内容は癌末期の痛みの緩和について痛み止めモルヒネなども用法に関して難解な話を解かり易くスライドを用いて講演された。中でもモルヒネはもっとも強力に効く痛み止めであるが、一般の開業医は以前からの経緯もあり殆ど使っていない。癌末期で痛みが取れない場合は主治医の力不足である。モルヒネはWHOの努力により世界的に普遍的に認められており、それなりに事前の手続きを取れば癌患者もモルヒネを持って持って海外旅行が可能で、各国の税関も通ることが出来るようになってきている。また、在宅で患者をみる場合、麻薬管理の許可を持っている医師の処方により調剤薬局でモルヒネを購入することも出来る。
参加者一同すっかり認識を新たにさせられ、講演の締めくくりはおくる心として、患者の終末は希望と生きがいにのある楽しい日々に、患者の美点を話し合い患者に満足すべき人生を安らかな死を患者も家族も受容することと、解説され参加者も目から鱗が落ちる思いであった。
事前の案内記事は行田市市報、毎日新聞、読売新聞、埼玉新聞に記載された。なを記事は翌日の19日の朝刊に「市民グループ、ホスピスを学ぶ」として副院長の写真入りで記載された。
副院長が「おくる心」と題して講演。内容は癌末期の痛みの緩和について痛み止めモルヒネなども用法に関して難解な話を解かり易くスライドを用いて講演された。中でもモルヒネはもっとも強力に効く痛み止めであるが、一般の開業医は以前からの経緯もあり殆ど使っていない。癌末期で痛みが取れない場合は主治医の力不足である。モルヒネはWHOの努力により世界的に普遍的に認められており、それなりに事前の手続きを取れば癌患者もモルヒネを持って持って海外旅行が可能で、各国の税関も通ることが出来るようになってきている。また、在宅で患者をみる場合、麻薬管理の許可を持っている医師の処方により調剤薬局でモルヒネを購入することも出来る。
参加者一同すっかり認識を新たにさせられ、講演の締めくくりはおくる心として、患者の終末は希望と生きがいにのある楽しい日々に、患者の美点を話し合い患者に満足すべき人生を安らかな死を患者も家族も受容することと、解説され参加者も目から鱗が落ちる思いであった。
事前の案内記事は行田市市報、毎日新聞、読売新聞、埼玉新聞に記載された。なを記事は翌日の19日の朝刊に「市民グループ、ホスピスを学ぶ」として副院長の写真入りで記載された。
![]() 前日に毎日新聞に広報掲載される。10月号、市報にも広報掲載される。 まず、院長よりこの会の成立と経過について約10分の説明があり、続いて戸倉 基さん(61歳)が沢山の資料を用意されて、1時間40分、熱の入った講演をされた。「私の癌闘病記」ということで9年前のS字結腸癌、2年前の肺癌について詳しく解説があり、また、生きがい療法を応用してのあくまで前向き闘病姿勢の実際をさまざまな小道具を使って説明された。その底抜けのあかるさ参加者一同、これが現に癌闘病中の患者かと驚くばかりであった。
続いて資料説明として金子より在宅ホスピスについて解説し質疑応答に入る。今回は時間を30分延長して4時半まで参加者より様々な質問を受けて、院長、副院長、講演者がこたえた。
初めて参加された男性から「こんな有意義な会とは知らなかった。次回も参加したい。」という発言があった。
前日に毎日新聞に広報掲載される。10月号、市報にも広報掲載される。 まず、院長よりこの会の成立と経過について約10分の説明があり、続いて戸倉 基さん(61歳)が沢山の資料を用意されて、1時間40分、熱の入った講演をされた。「私の癌闘病記」ということで9年前のS字結腸癌、2年前の肺癌について詳しく解説があり、また、生きがい療法を応用してのあくまで前向き闘病姿勢の実際をさまざまな小道具を使って説明された。その底抜けのあかるさ参加者一同、これが現に癌闘病中の患者かと驚くばかりであった。
続いて資料説明として金子より在宅ホスピスについて解説し質疑応答に入る。今回は時間を30分延長して4時半まで参加者より様々な質問を受けて、院長、副院長、講演者がこたえた。
初めて参加された男性から「こんな有意義な会とは知らなかった。次回も参加したい。」という発言があった。